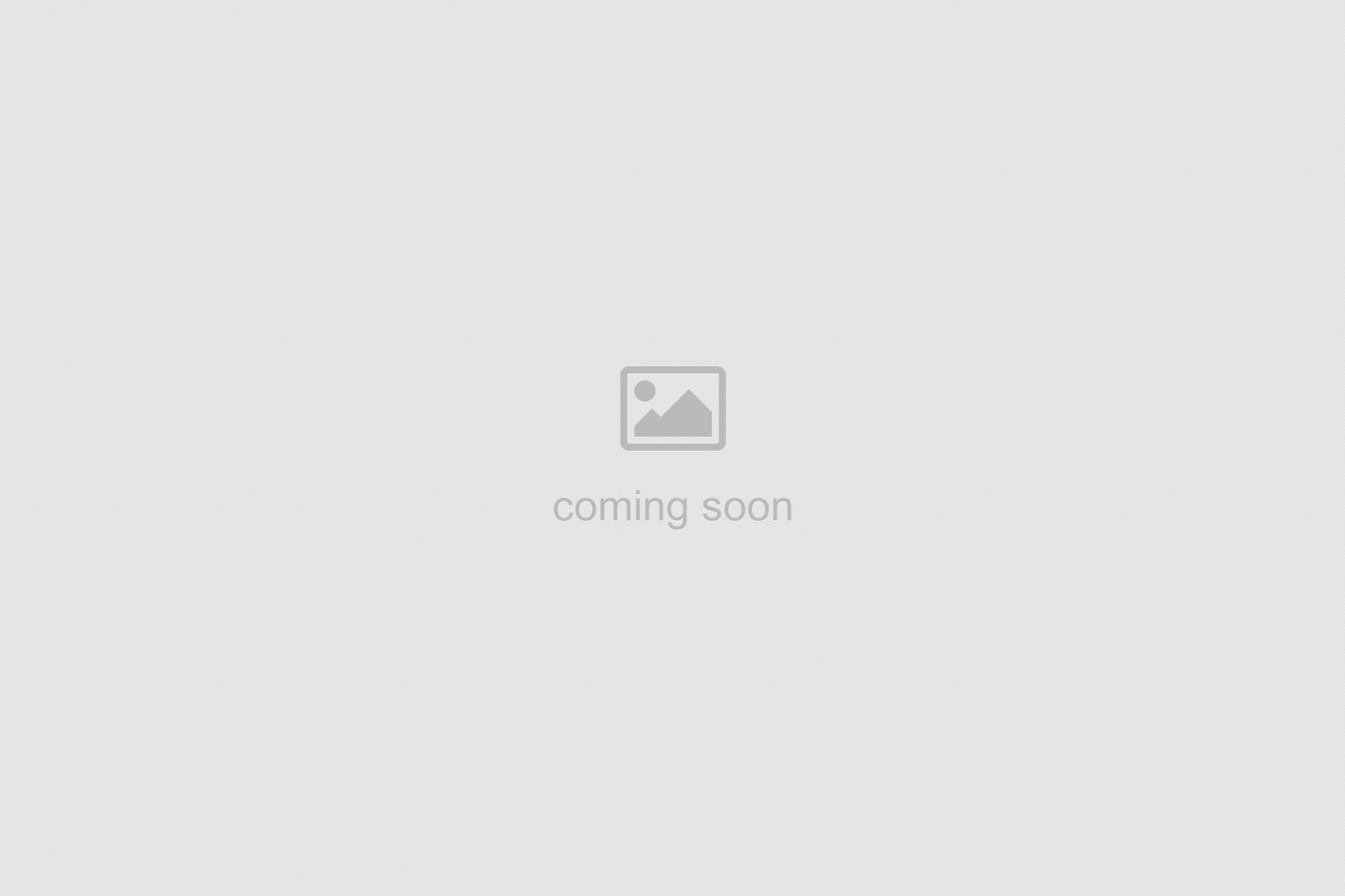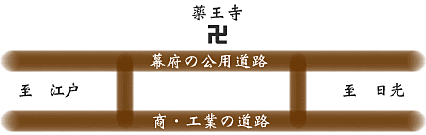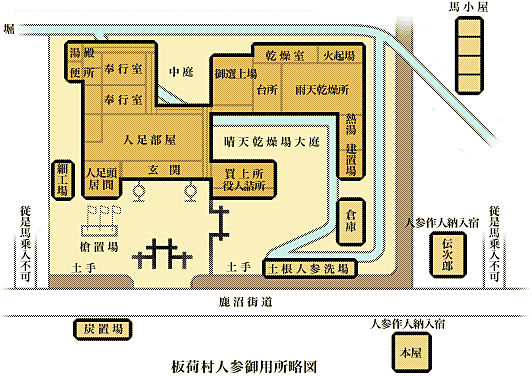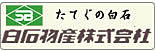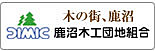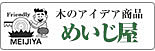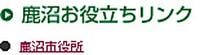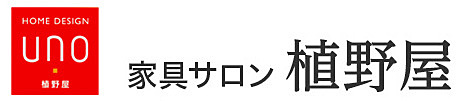木目のコラム 木工の町鹿沼の歴史
その一
鹿沼市は県都、宇都宮の西約20キロ日光の南30キロ栃木県のやや中央に位置しています。有史以前の謎を秘めて市内に散在する幾多の遺跡、遺物が発掘され古くから人々の生活が営まれていたことが伺われます。今回は豊臣秀吉が日本統一を目前にして小田原の北条氏を攻めた時の鹿沼から話をすすめることにします。
壬生氏「現壬生町から起きた豪族」によって鹿沼城が築かれたのは天文元年「千五百三二年」であります、しかし天正十八年秀吉の小田原攻めのおりは北条方に味方していたため壬生義雄は、出陣し酒匂川において三十九歳で陣没します。壬生氏は秀吉の意に叶わず取り潰しとなり、壬生城は前田利家の軍に開けわたされます。鹿沼城はこれより早く四月十七日に宇都宮勢によって攻められ落城したと伝えられています。義雄の遺品は壬生町の雄琴神社の神宝としていまに伝えられています。鹿沼には鹿沼城最後の城主であったことで、しるしの石塔が西鹿沼 雄山寺にあります。殉死 若林蔵人 外家臣の塚もそこにあります。
壬生氏は五代 百三十年で滅亡家臣の多くが帰農しました。その後の鹿沼は結城氏の支配下に置かれました。
壬生氏「現壬生町から起きた豪族」によって鹿沼城が築かれたのは天文元年「千五百三二年」であります、しかし天正十八年秀吉の小田原攻めのおりは北条方に味方していたため壬生義雄は、出陣し酒匂川において三十九歳で陣没します。壬生氏は秀吉の意に叶わず取り潰しとなり、壬生城は前田利家の軍に開けわたされます。鹿沼城はこれより早く四月十七日に宇都宮勢によって攻められ落城したと伝えられています。義雄の遺品は壬生町の雄琴神社の神宝としていまに伝えられています。鹿沼には鹿沼城最後の城主であったことで、しるしの石塔が西鹿沼 雄山寺にあります。殉死 若林蔵人 外家臣の塚もそこにあります。
壬生氏は五代 百三十年で滅亡家臣の多くが帰農しました。その後の鹿沼は結城氏の支配下に置かれました。
その二 秀吉の好色、鹿沼の衰退
関東の雄 北条氏はあっけなく滅んだ。150年 民政に力を注ぎ枝城、属城 約50 300万石の覇者も、秀吉の津波のごとき大軍と物量に圧倒されたのでありましょう。そして小田原評定という芳しくない話だけが残りました。
前回ふれました壬生氏も北条氏も殉じましたが、皆川と鎌倉時代からの名家小山氏も所領没収となります。7月古河に入った秀吉の仕置きは続きます。ここで足利氏にふれます。足利尊氏によってできた室町幕府は東国を治める関東管領を置きましたが相次ぐ下克上と戦乱によって衰退し、9才の姫1人を残すのみとなりました。
関東管領の分かれに小弓御所があり、その出自のお嶋は塩谷惟久に嫁いでいましたが、塩谷は秀吉の武威に恐れて那須の山に側室を連れて逃れ、主にかわって秀吉に謁見したのがお嶋でありました。
秀吉54才お嶋23才 お嶋は己を秀吉に献じて足利の存続をはかります。京の足利将軍は信長によって既に亡く、いまや足利の血脈は9才の氏姫1人という風前の灯火。お嶋の決断と秀吉の好色がさまざまな波乱をへながらも、現代まで源氏の名家の血統を絶やすことはありませんでした。
秀吉は化粧料として、喜連川に3800石を与え会津にむかいます。氏姫は古河で成長してゆき、やがてお嶋の弟頼氏と夫婦となります、喜連川は徳川の時代も源氏の血筋として客分扱いされ大切にされました。お嶋は秀吉が死んだ年、京都で尼となり翌年江戸に庵をむすび88才まで生きた。フジテレビのそばにある月桂寺に墓があります。古河市と喜連川町は姉妹都市として交流しています。
前回ふれました壬生氏も北条氏も殉じましたが、皆川と鎌倉時代からの名家小山氏も所領没収となります。7月古河に入った秀吉の仕置きは続きます。ここで足利氏にふれます。足利尊氏によってできた室町幕府は東国を治める関東管領を置きましたが相次ぐ下克上と戦乱によって衰退し、9才の姫1人を残すのみとなりました。
関東管領の分かれに小弓御所があり、その出自のお嶋は塩谷惟久に嫁いでいましたが、塩谷は秀吉の武威に恐れて那須の山に側室を連れて逃れ、主にかわって秀吉に謁見したのがお嶋でありました。
秀吉54才お嶋23才 お嶋は己を秀吉に献じて足利の存続をはかります。京の足利将軍は信長によって既に亡く、いまや足利の血脈は9才の氏姫1人という風前の灯火。お嶋の決断と秀吉の好色がさまざまな波乱をへながらも、現代まで源氏の名家の血統を絶やすことはありませんでした。
秀吉は化粧料として、喜連川に3800石を与え会津にむかいます。氏姫は古河で成長してゆき、やがてお嶋の弟頼氏と夫婦となります、喜連川は徳川の時代も源氏の血筋として客分扱いされ大切にされました。お嶋は秀吉が死んだ年、京都で尼となり翌年江戸に庵をむすび88才まで生きた。フジテレビのそばにある月桂寺に墓があります。古河市と喜連川町は姉妹都市として交流しています。
その三 徳川家康没して鹿沼のまちづくり
元和二年四月一七日、家康は後に”人の一生は重き荷を負うて遠き道を行くが如し”と言われるごとくの生涯を閉じます。その夜のうちに久能山に葬られたと言われます。今の習慣からみればずいぶん早いと思いますが秀吉もやはり、その夜に葬られたとありますから、当時の慣例だったのでしょう。
これより三年前、僧天海が日光山の貫首となっておりましたから家康生前からの計らいであったのでしょう。幕府は日光に東照社の造営に着手しました、造営奉行・藤堂高虎でした。
秀吉軍に攻められて落城した城のまわりには十年程たって鹿沼の氏神今宮神社の再建をしました。人々の暮らしが安定してきたのでしょう。
さらに十五年が過ぎ、天下は次の時代へと移り再び日光に陽があたります。つれて鹿沼も人々の往来が増え賑わいを少しずつとりもどしてゆきます。支配者も結城氏から徳川の代官、大河内金兵衛秀綱になっていました。金兵衛はこの時七十有余才になっていましたが最後のご奉公と老骨を自ら励まし、日光街道の整備に取り組みました。住民のなかからも、鹿沼再建に立ち上がった人々がいました。鈴木兵庫之丞・篠田半左衛門・問屋利右衛門・伊矢野藤左衛門・伊矢野助左衛門○○団之助・波田野藤左衛門・○○太郎左衛門・松島宗休・伊矢野清左衛門・柳田四郎左衛門・竹沢○○・椎谷次郎之進・座原弥左衛門・船越文弥・早乙女茂左衛門・大谷与惣次の十七人でした。
金兵衛 頑張って 頑張れ まちおこしの元祖
これより三年前、僧天海が日光山の貫首となっておりましたから家康生前からの計らいであったのでしょう。幕府は日光に東照社の造営に着手しました、造営奉行・藤堂高虎でした。
秀吉軍に攻められて落城した城のまわりには十年程たって鹿沼の氏神今宮神社の再建をしました。人々の暮らしが安定してきたのでしょう。
さらに十五年が過ぎ、天下は次の時代へと移り再び日光に陽があたります。つれて鹿沼も人々の往来が増え賑わいを少しずつとりもどしてゆきます。支配者も結城氏から徳川の代官、大河内金兵衛秀綱になっていました。金兵衛はこの時七十有余才になっていましたが最後のご奉公と老骨を自ら励まし、日光街道の整備に取り組みました。住民のなかからも、鹿沼再建に立ち上がった人々がいました。鈴木兵庫之丞・篠田半左衛門・問屋利右衛門・伊矢野藤左衛門・伊矢野助左衛門○○団之助・波田野藤左衛門・○○太郎左衛門・松島宗休・伊矢野清左衛門・柳田四郎左衛門・竹沢○○・椎谷次郎之進・座原弥左衛門・船越文弥・早乙女茂左衛門・大谷与惣次の十七人でした。
金兵衛 頑張って 頑張れ まちおこしの元祖
その四 徳川家康の柩 鹿沼に5日間安置される
金兵衛と17人の宿づくりは井桁の道をつくりました。
日光はすでに大規模な工事がはじまって諸国から人々の往来が多く幕閣要人などは供揃えをして日光に向かい、先触れの家士が走るようにして通り過ぎ、職人たちが商い道へ寄り飯をかき込むようにして食べ、足を速めて通り過ぎて行ったことでしょう。
東照宮造営の「元和の造営」邪魔になってはいけないということで道が二筋できたのでしょう。
元和3年3月15日東照社竣工「当時は宮ではなく社」鹿沼の古記録には竣工の日に久能より御尊骸を日光山に移し奉る。将軍秀忠公の御名代には、従四位少将土井大炊頭源利勝「中略」をはじめ英士、雑色に至るまで綺羅を尽くして供奉し奉る。大僧正天海 御導師として金輿に御先達。「中略」栃木という里を過ぎて室の八嶋を右になし、鹿沼にて薬王寺といへる寺に入らせ給う。この所に中3日御逗留。3月29日より4月4日迄此所の御安座あり、と書き残されています。
豪華絢爛な葬列が鹿沼宿を立ちますが、その後に陸続として供奉の列が続きます、もうかと思えばまだまだ終日続きます。
落城から25年たって此の地に希望の灯りがともりました。よかったね。
日光はすでに大規模な工事がはじまって諸国から人々の往来が多く幕閣要人などは供揃えをして日光に向かい、先触れの家士が走るようにして通り過ぎ、職人たちが商い道へ寄り飯をかき込むようにして食べ、足を速めて通り過ぎて行ったことでしょう。
東照宮造営の「元和の造営」邪魔になってはいけないということで道が二筋できたのでしょう。
元和3年3月15日東照社竣工「当時は宮ではなく社」鹿沼の古記録には竣工の日に久能より御尊骸を日光山に移し奉る。将軍秀忠公の御名代には、従四位少将土井大炊頭源利勝「中略」をはじめ英士、雑色に至るまで綺羅を尽くして供奉し奉る。大僧正天海 御導師として金輿に御先達。「中略」栃木という里を過ぎて室の八嶋を右になし、鹿沼にて薬王寺といへる寺に入らせ給う。この所に中3日御逗留。3月29日より4月4日迄此所の御安座あり、と書き残されています。
豪華絢爛な葬列が鹿沼宿を立ちますが、その後に陸続として供奉の列が続きます、もうかと思えばまだまだ終日続きます。
落城から25年たって此の地に希望の灯りがともりました。よかったね。
その五 秀忠、釣り天井を避け鹿沼を駆け抜ける
元和八年四月、日光東照社奥社・宝塔完成。家康公の七回忌に、秀忠社参に向かいます。
江戸を出て小山・宇都宮・今市そして日光と滞りなく、すべてが終わったその夜、近侍の者が伺候して一大事にござりまする、さらに声をひそめて、本多正純殿ご謀反の企てありとの報がありましてござります。翌、夜の明けきらぬ中数人の供と秀忠は日光を脱出します。今市で道を右にとり板橋から鹿沼を駆け抜け、その日のうちに江戸城に帰り着いたと言われています。
正純は幼い時から家康に仕えた股肱の臣、関ヶ原の時は37才家康の帷幕にあって働き、大阪城の堀の埋め立て奉行として辣腕をふるい豊臣の滅亡を早めた。
その地位は昇りつめて幕閣の中枢となり2年前に宇都宮15万5千石の藩主となりました。
城の修築の際、根本衆を多数殺害する、また大谷石を多量に使ったことなどが、秘密の工事に関わった者の口封じ、天井の石を落とし秀忠暗殺を企てた。という宇都宮釣り天井の伝説はこの時に起きたものです。
真実は今となっては闇の中、誰かの讒言によるものか、幕閣の陰謀に秀忠が演出したのか、翌年家光が将軍に就きました。江戸城は権謀、術策の渦巻く所でもあったのでしょう。
八月正純はこの事により出羽に流され、15年後73才で没しました。
故事に曰く、獲物を捕り尽くせば猟犬煮られる。
以前には宇都宮の菓子に「釣り天井」というものがありましたが一時期のことで、今は有りません。どんな味だったのでしょうか、覚えておりません。
一方天海さん家康公の葬儀の時82才、本多正純の死んだ時には102才、そして6年後108才で没します。
長生きの秘訣をお聞きすると
”気は長く 勤めはかたく 色うすく 食ほそうして 心ひろかれ”
ときの天皇より、慈眼大師の号を賜る、日光の慈眼堂に墓があります。
江戸を出て小山・宇都宮・今市そして日光と滞りなく、すべてが終わったその夜、近侍の者が伺候して一大事にござりまする、さらに声をひそめて、本多正純殿ご謀反の企てありとの報がありましてござります。翌、夜の明けきらぬ中数人の供と秀忠は日光を脱出します。今市で道を右にとり板橋から鹿沼を駆け抜け、その日のうちに江戸城に帰り着いたと言われています。
正純は幼い時から家康に仕えた股肱の臣、関ヶ原の時は37才家康の帷幕にあって働き、大阪城の堀の埋め立て奉行として辣腕をふるい豊臣の滅亡を早めた。
その地位は昇りつめて幕閣の中枢となり2年前に宇都宮15万5千石の藩主となりました。
城の修築の際、根本衆を多数殺害する、また大谷石を多量に使ったことなどが、秘密の工事に関わった者の口封じ、天井の石を落とし秀忠暗殺を企てた。という宇都宮釣り天井の伝説はこの時に起きたものです。
真実は今となっては闇の中、誰かの讒言によるものか、幕閣の陰謀に秀忠が演出したのか、翌年家光が将軍に就きました。江戸城は権謀、術策の渦巻く所でもあったのでしょう。
八月正純はこの事により出羽に流され、15年後73才で没しました。
故事に曰く、獲物を捕り尽くせば猟犬煮られる。
以前には宇都宮の菓子に「釣り天井」というものがありましたが一時期のことで、今は有りません。どんな味だったのでしょうか、覚えておりません。
一方天海さん家康公の葬儀の時82才、本多正純の死んだ時には102才、そして6年後108才で没します。
長生きの秘訣をお聞きすると
”気は長く 勤めはかたく 色うすく 食ほそうして 心ひろかれ”
ときの天皇より、慈眼大師の号を賜る、日光の慈眼堂に墓があります。
その六
戦乱が収まり、鹿沼の町づくりも一応おわり、宿場を様々な人々が通り過ぎて行くうちに時代も過ぎて行きます。金兵衛と供に働いた17人も次の代となっていました。
伊矢野家はもと矢野と言い鹿沼没落の後、小山の大名に供奉したが小山落城後は鹿沼に戻り伊の字を頭に付けて伊矢野と名乗ることになりました。
矢野修理祐は伊矢野与作郎とその名を改め、表口 百間余の屋敷を造りました。
世間の人は与作郎どのは金銀をどれだけ持っているのか自分でもわからないようだ、と噂し会った。又金の使い方を知らないのでこんな風にしていると評判になった。それは女十二人を召し抱えてすべてが器量よく年頃もおなじ、衣服・櫛・簪・手ぬぐいまですべてがお揃いで区別が付かない、給金は望みしだいで、百、二百両と払っているらしい。
江戸の人が日光参詣のおり鹿沼の与作郎宅でご馳走になった時、同じ女中が次からつぎと現れるのには驚き古今話にも聞いたことがない、江戸にもどってこの話をしたところ、いつしか唄ができた。
「関八州で良い女が見たけりゃ下野鹿沼の田宿与作どんへ御座れ」
宝永年間、相州小田原に旅をした鹿沼の人が石臼ひき唄を聞いてきたと地元でもそのことに改めて評判になったようです。やがて与作郎は隠居して宋丹と名乗って髪もおろします。家業の造り酒屋は倅の平右衛門が継ぎますが、元禄の頃火災にあって七つの蔵全てが焼けたと記録されています。
金子がぞろり流れ出ていたので、もがりから中に入った所、叱られてしまったので、逃げ出した覚えがあります、私が七つか八つの頃でした。
鹿沼古記録にはこう書き残されています。
その子孫は今でも健在、普通の人です。
伊矢野家はもと矢野と言い鹿沼没落の後、小山の大名に供奉したが小山落城後は鹿沼に戻り伊の字を頭に付けて伊矢野と名乗ることになりました。
矢野修理祐は伊矢野与作郎とその名を改め、表口 百間余の屋敷を造りました。
世間の人は与作郎どのは金銀をどれだけ持っているのか自分でもわからないようだ、と噂し会った。又金の使い方を知らないのでこんな風にしていると評判になった。それは女十二人を召し抱えてすべてが器量よく年頃もおなじ、衣服・櫛・簪・手ぬぐいまですべてがお揃いで区別が付かない、給金は望みしだいで、百、二百両と払っているらしい。
江戸の人が日光参詣のおり鹿沼の与作郎宅でご馳走になった時、同じ女中が次からつぎと現れるのには驚き古今話にも聞いたことがない、江戸にもどってこの話をしたところ、いつしか唄ができた。
「関八州で良い女が見たけりゃ下野鹿沼の田宿与作どんへ御座れ」
宝永年間、相州小田原に旅をした鹿沼の人が石臼ひき唄を聞いてきたと地元でもそのことに改めて評判になったようです。やがて与作郎は隠居して宋丹と名乗って髪もおろします。家業の造り酒屋は倅の平右衛門が継ぎますが、元禄の頃火災にあって七つの蔵全てが焼けたと記録されています。
金子がぞろり流れ出ていたので、もがりから中に入った所、叱られてしまったので、逃げ出した覚えがあります、私が七つか八つの頃でした。
鹿沼古記録にはこう書き残されています。
その子孫は今でも健在、普通の人です。
その七 徳川家光はお爺ちゃんが大好き
元和9年(1623)家康の命日に家光は最初の日光社参をします。
そして家康の33回忌の慶安元年までの25年間に10回も社参しました。寛永11年(1634)には東照社の大造営に着手し翌年4月竣工、この時の建築物が今の東照宮です。この時家光は7回目の社参をします。供奉には御三家をはじめ幕閣20余、外様大名も加わりその行列は壮麗を極めたと言われています。
日光に何か行事があるたびに鹿沼宿を人々が通りますが、寛永の大造営には1万6千人が工事にたずさわったと言われていますから、各街道にそして宿場に賑わいと潤いを残したことでしょう。さらにこの年、朝鮮通信使「いまの言葉では親善使」が参拝に来て一層の賑わいとなりました。
正保4年例幣使が朝廷より派遣されるようになり、以後220年間明治になるまで毎年4月1日京を出立して中山道を通り倉賀野から分かれて楡木・鹿沼を経て15日には東照宮参拝して帰路は宇都宮から江戸に向かいます。例幣使は古来から伊勢だけに派遣されていたものが東照宮にも来るようになりました。家光は祖父が好きというより徳川幕府の安泰、再び戦のない世の中を願って家康の神格化に努めたと思います。それが東照宮の大造営となり、例幣使の派遣により益々高められたことでしょう。このころは亡き大御所とは言わず、東照神君となっていたのでしょう。慶安4年4月20日家光は48才で没します。
鹿沼の古文書にはこう書き残されています。
同月21日の黄昏に御尊像を営中より東叡山に本坊に移し奉り、24日宝館を出御なしたてまつる、左近衛少将・酒井讃岐守・源忠勝「中略」其のほか近習外様の英士数多く供奉。今日のお泊まりは粕壁・最勝院、25日は栗橋・福寿院、26日は真々田・竜昌寺、27日は鹿沼・薬王寺と家光の葬列が延々鹿沼宿を通過していきますが家康の葬列以来35年後のことでありました。
JR日光線・東武日光線ともに徳川家光のおかげです。
家光の墓所がある大猷院もかなりのものです、世界遺産だけありますね。
そして家康の33回忌の慶安元年までの25年間に10回も社参しました。寛永11年(1634)には東照社の大造営に着手し翌年4月竣工、この時の建築物が今の東照宮です。この時家光は7回目の社参をします。供奉には御三家をはじめ幕閣20余、外様大名も加わりその行列は壮麗を極めたと言われています。
日光に何か行事があるたびに鹿沼宿を人々が通りますが、寛永の大造営には1万6千人が工事にたずさわったと言われていますから、各街道にそして宿場に賑わいと潤いを残したことでしょう。さらにこの年、朝鮮通信使「いまの言葉では親善使」が参拝に来て一層の賑わいとなりました。
正保4年例幣使が朝廷より派遣されるようになり、以後220年間明治になるまで毎年4月1日京を出立して中山道を通り倉賀野から分かれて楡木・鹿沼を経て15日には東照宮参拝して帰路は宇都宮から江戸に向かいます。例幣使は古来から伊勢だけに派遣されていたものが東照宮にも来るようになりました。家光は祖父が好きというより徳川幕府の安泰、再び戦のない世の中を願って家康の神格化に努めたと思います。それが東照宮の大造営となり、例幣使の派遣により益々高められたことでしょう。このころは亡き大御所とは言わず、東照神君となっていたのでしょう。慶安4年4月20日家光は48才で没します。
鹿沼の古文書にはこう書き残されています。
同月21日の黄昏に御尊像を営中より東叡山に本坊に移し奉り、24日宝館を出御なしたてまつる、左近衛少将・酒井讃岐守・源忠勝「中略」其のほか近習外様の英士数多く供奉。今日のお泊まりは粕壁・最勝院、25日は栗橋・福寿院、26日は真々田・竜昌寺、27日は鹿沼・薬王寺と家光の葬列が延々鹿沼宿を通過していきますが家康の葬列以来35年後のことでありました。
JR日光線・東武日光線ともに徳川家光のおかげです。
家光の墓所がある大猷院もかなりのものです、世界遺産だけありますね。
その八 鹿沼の消費と経済はこうして変わっていった
江戸から河川水路を利用して乙女河岸「間々田」に来て思川をさかのぼって、壬生に来て陸揚げされる。 壬生から四里「16キロ」鹿沼までは陸送されます。家康・秀忠・家光のころの内町通りは御公儀が最優先され物を売るのは立ち売りのみが許されましたが、いつしか板戸を並べて商いをするようになり、元禄の頃には諸人の往来も増えてきます。さらに例幣使の通行もあって内町も店を持って商いをする者が出てきました。
元禄6年内町の藤作と田町の佐五兵衛という2人が共同して内町に穀問屋を開いたところ、田町の穀屋13人が藤作の店に来て「昔から穀問屋はそれぞれ13人が祖先の代より、お上から許されて穀座の株を持っているものである、しかるにお上のお許しなく穀問屋を始めるは、もってのほか」と、藤作が商売をできなくしてしまった。今度は藤作と佐五兵衛がお上に訴える事件i昧になった。
結果、古来から穀座は田町であることが確定され、田町の13人に内町の4人を加えて決着した。
元禄8年、内町通りのほうには益々人通りが増えて商いが活発になって行きます。当然の事ながら商品も増えてきて商人は富裕となっていきます。
田町の人々は古来からの先例に依存しすぎた。元禄8年田町側からお上に訴えがあった。古来より両通りとも商いの方法と商品がお上によって決められている。内町はそれに背き商売をしている。取り締まって欲しい、というものであった。これに対して結果は、田町は木綿・古着・紙・茶・細工物・ネギ・ニンニク・炭・鍬・鎌、内町は麻・小間物・塩・竹木・たばこ・真綿と決まった。これを元禄の品分けと言った。内町に麻のお許しが入った。後にこの麻は300年も鹿沼を支えた大きな産業になろうとはこの時誰も予想をしなかった。
徳川家光の葬列が鹿沼を通ってから45年後のことでした。
壬生氏は五代 百三十年で滅亡家臣の多くが帰農しました。その後の鹿沼は結城氏の支配下に置かれました。
元禄6年内町の藤作と田町の佐五兵衛という2人が共同して内町に穀問屋を開いたところ、田町の穀屋13人が藤作の店に来て「昔から穀問屋はそれぞれ13人が祖先の代より、お上から許されて穀座の株を持っているものである、しかるにお上のお許しなく穀問屋を始めるは、もってのほか」と、藤作が商売をできなくしてしまった。今度は藤作と佐五兵衛がお上に訴える事件i昧になった。
結果、古来から穀座は田町であることが確定され、田町の13人に内町の4人を加えて決着した。
元禄8年、内町通りのほうには益々人通りが増えて商いが活発になって行きます。当然の事ながら商品も増えてきて商人は富裕となっていきます。
田町の人々は古来からの先例に依存しすぎた。元禄8年田町側からお上に訴えがあった。古来より両通りとも商いの方法と商品がお上によって決められている。内町はそれに背き商売をしている。取り締まって欲しい、というものであった。これに対して結果は、田町は木綿・古着・紙・茶・細工物・ネギ・ニンニク・炭・鍬・鎌、内町は麻・小間物・塩・竹木・たばこ・真綿と決まった。これを元禄の品分けと言った。内町に麻のお許しが入った。後にこの麻は300年も鹿沼を支えた大きな産業になろうとはこの時誰も予想をしなかった。
徳川家光の葬列が鹿沼を通ってから45年後のことでした。
壬生氏は五代 百三十年で滅亡家臣の多くが帰農しました。その後の鹿沼は結城氏の支配下に置かれました。
その九 天朝さまのお使いが通る
例幣使は古来朝廷から伊勢神宮へ遣わされていました。正保3年1646年日光東照宮へ参向して以来慶応3年まで、221年続いた。
毎年4月1日京を出立して東海道を草津から中山道に入り、木曽路を越え倉賀野から分かれて玉村・八木(八木節発祥の地)・大田・梁田(足利市)・天明(佐野市)・富田(大平下)・栃木・合戦場・金崎・楡木の23里、92キロこの間を例幣使街道といいます。
ここで日光街道壬生通りと合流します。今夜の泊まりは鹿沼宿はもうそこ幣使に加えて京の商人、荷駄、前後には道中に係わる藩などの警護などなど総勢200人余りとなった。幣使が用意してきた、御供米5~6粒を一包みとして2万包みは鹿沼に着く頃にはかなり減ってきています。宿では公家の入った風呂の水を厄除け薬として売ったという話も残っています。
幣使の一行に商人たち、米屋、魚屋、八百屋などが同行しているのは貧乏公家の集金が京ではできないので、例幣使の機会をのがさず同行して幣使の変わりに集金して歩いた。これが御供米だったのです。それがためには幣使は天子様の御名代、参議がなります権威をより高く、威厳を保つ演出も必要でありました。
迎える方は毎年4月になると、道普請が始まり前日には川砂が撒かれ、町役人、町年寄りは手配万端に気を遣います。こうしたことが200年あまりも続いたのは、係わる人すべてが何らかの利益があったからでしょう。幕府は朝廷から幣使が来ることによる権威、幣使は一度東照宮に使いすれば一釜起こす、と言われるほどのおいしい役目、商人たちは日光見物を兼ねての集金旅行、迎える方も白粉をつけた都の男を一目見ようと人が出る、金も動く、なにより京の文化に触れる誇りがあったのでしょう。
4月15日日光に着く。16日暁に沐浴して輿で石鳥居まで行き陽明門から唐門へと進み手水をつかい、拝殿階下で沓を脱ぎ剣は帯びたまま中央に着座する。参拝して宣命を高く奉じて、奉読したのち奉幣の儀を行う、これで幣使の役目は大体終わる。あとは前年の幣を細かに分け、東照大権現ご神体として江戸の大名達に売りつける仕事が残っている。
今、こんなお使いどこかにありませんか?
毎年4月1日京を出立して東海道を草津から中山道に入り、木曽路を越え倉賀野から分かれて玉村・八木(八木節発祥の地)・大田・梁田(足利市)・天明(佐野市)・富田(大平下)・栃木・合戦場・金崎・楡木の23里、92キロこの間を例幣使街道といいます。
ここで日光街道壬生通りと合流します。今夜の泊まりは鹿沼宿はもうそこ幣使に加えて京の商人、荷駄、前後には道中に係わる藩などの警護などなど総勢200人余りとなった。幣使が用意してきた、御供米5~6粒を一包みとして2万包みは鹿沼に着く頃にはかなり減ってきています。宿では公家の入った風呂の水を厄除け薬として売ったという話も残っています。
幣使の一行に商人たち、米屋、魚屋、八百屋などが同行しているのは貧乏公家の集金が京ではできないので、例幣使の機会をのがさず同行して幣使の変わりに集金して歩いた。これが御供米だったのです。それがためには幣使は天子様の御名代、参議がなります権威をより高く、威厳を保つ演出も必要でありました。
迎える方は毎年4月になると、道普請が始まり前日には川砂が撒かれ、町役人、町年寄りは手配万端に気を遣います。こうしたことが200年あまりも続いたのは、係わる人すべてが何らかの利益があったからでしょう。幕府は朝廷から幣使が来ることによる権威、幣使は一度東照宮に使いすれば一釜起こす、と言われるほどのおいしい役目、商人たちは日光見物を兼ねての集金旅行、迎える方も白粉をつけた都の男を一目見ようと人が出る、金も動く、なにより京の文化に触れる誇りがあったのでしょう。
4月15日日光に着く。16日暁に沐浴して輿で石鳥居まで行き陽明門から唐門へと進み手水をつかい、拝殿階下で沓を脱ぎ剣は帯びたまま中央に着座する。参拝して宣命を高く奉じて、奉読したのち奉幣の儀を行う、これで幣使の役目は大体終わる。あとは前年の幣を細かに分け、東照大権現ご神体として江戸の大名達に売りつける仕事が残っている。
今、こんなお使いどこかにありませんか?
その十 天下太平祭りだ祭りだ
元禄の頃から作付けが始まった麻は、しだいに各地に広まり、鹿沼は麻の産地としての名声を高めて行きました。八代将軍吉宗の頃には麻の産業は庶民のものとなってきました。さらに80年も過ぎた文化年間には鹿沼宿の家数は735軒となり、其の7割が商い渡世またそれを兼ねていたようです。
職業も多いほうは麻・米・穀物・荒物・質屋・醤油・水油・旅籠・桶屋などなど70業種にもおよびました。幕府は無用の食物商いはやめるように倹約令を度々だしますが居酒屋とか茶屋(今の喫茶店)など庶民の欲望を抑えることはできず、次第に増えて行きました。文化2年鹿沼は戸田越前守が支配していました。その時の幕府への報告書にこう残されています。
石高 1699石4斗
本陣 建坪 96坪 玄関付 門構え
旅籠 28軒 内 大 1軒 中 1軒 小 26軒 などなど
当所名産麻の儀、近在にて作り候にて、鹿沼麻と唱え、江戸・京・大阪・濱方(千葉房総)まで当所商人共より売り出しもうし候。
男女農業のほか男は近郷の市で商いつかまつり在所より麻・たばこのようなものを買い出しにまかりいで、女は麻糸、畳糸など手業つかまつり候。
今から200年ほど前の宿場の様子がうかがえられます。京、大阪まで商いの手を広げた商人によって鹿沼の庶民まで潤ってきました。
鹿沼の氏神は北条氏のとき二荒山神社の分祀を遷座したものが今宮神社であります。日光の弥生祭にならい、古式豊かな神輿の渡御をしていましたが、踊り屋台が造られ町ごとに踊りや狂言などを競い庶民のものとなってゆきました。文化年間1812年ごろ彫刻屋台が造られます。華美から豪華に変わってきました。財力も伴ってのことでしょう。
以来、文政、天保、文久、明治、昭和、平成の今まで彫刻屋台は作り続けられ、今その数27台となっています。お囃子は屋台を持たない近在の人々がそれぞれの流儀があり、伝承してきた囃子方を競い合います。十字路で屋台が出会うときはその頂点に達します。
毎年10月の第2土曜~日曜日です。
祭り好きな方はどうぞお越しを!
職業も多いほうは麻・米・穀物・荒物・質屋・醤油・水油・旅籠・桶屋などなど70業種にもおよびました。幕府は無用の食物商いはやめるように倹約令を度々だしますが居酒屋とか茶屋(今の喫茶店)など庶民の欲望を抑えることはできず、次第に増えて行きました。文化2年鹿沼は戸田越前守が支配していました。その時の幕府への報告書にこう残されています。
石高 1699石4斗
本陣 建坪 96坪 玄関付 門構え
旅籠 28軒 内 大 1軒 中 1軒 小 26軒 などなど
当所名産麻の儀、近在にて作り候にて、鹿沼麻と唱え、江戸・京・大阪・濱方(千葉房総)まで当所商人共より売り出しもうし候。
男女農業のほか男は近郷の市で商いつかまつり在所より麻・たばこのようなものを買い出しにまかりいで、女は麻糸、畳糸など手業つかまつり候。
今から200年ほど前の宿場の様子がうかがえられます。京、大阪まで商いの手を広げた商人によって鹿沼の庶民まで潤ってきました。
鹿沼の氏神は北条氏のとき二荒山神社の分祀を遷座したものが今宮神社であります。日光の弥生祭にならい、古式豊かな神輿の渡御をしていましたが、踊り屋台が造られ町ごとに踊りや狂言などを競い庶民のものとなってゆきました。文化年間1812年ごろ彫刻屋台が造られます。華美から豪華に変わってきました。財力も伴ってのことでしょう。
以来、文政、天保、文久、明治、昭和、平成の今まで彫刻屋台は作り続けられ、今その数27台となっています。お囃子は屋台を持たない近在の人々がそれぞれの流儀があり、伝承してきた囃子方を競い合います。十字路で屋台が出会うときはその頂点に達します。
毎年10月の第2土曜~日曜日です。
祭り好きな方はどうぞお越しを!
その十一 薬用人参の栽培で吉宗さまさま
八代将軍吉宗の時代、享保13年(1728)日光の七里という所で栽培していた人参は、気候が適していたため次第に軌道に乗って来ました。幕府もこれをいっそう奨励したので、作付け地も増えて、日光と同じ寒冷気候の鹿沼の北西部、板荷にも人参の栽培が広がってきました。寛政12年、幕府は板荷に人参製法所を作ります。
地元の人は人参奉行所と呼んだ。
人参作人は1,000人にも及び、世話人は100人となり、鹿沼近郷の村々に作付けは広がって行きました。
世話人は、人参の種から管理する人で、蒔付量は2000粒までとされて発芽はどうか、2年生は何程、3年生は何程、毎年9月には4年生で掘り出し、これを奉行に報告する。その上で人参製法所へ持っていき、上・中・下と選別される。
人参を隠したり勝手に売買したりする事が無いように、厳重な管理の基にすべてが行われたようです。
各村から持ち込まれる土人参の選別、格付け、水洗い、湯通し、陰干し、江戸への輸送と、将軍家御用という重責の下に、異郷に倒れた奉行の墓は、板荷の観音寺に三基並んであります。没月はいづれも繁忙期の8月、9月でした。
徳川幕府の人参への関与は、明治2年で終わりを告げます。
幕府崩壊して買い手を失った人参栽培者は、それでも作り続けるしかありませんでした。やがて、明治資本主義の萌芽と共に、再び人参に陽が当たる様になります。日光人参として今の中国へ輸出されました。
代表する人物は、安田善次郎でありましたが、地元からも人参から得た資金を、後年、麻産業の近代化を興し、当時財界で重きをなした鈴木要三も人参世話人の家系でした。
地元の人は人参奉行所と呼んだ。
人参作人は1,000人にも及び、世話人は100人となり、鹿沼近郷の村々に作付けは広がって行きました。
世話人は、人参の種から管理する人で、蒔付量は2000粒までとされて発芽はどうか、2年生は何程、3年生は何程、毎年9月には4年生で掘り出し、これを奉行に報告する。その上で人参製法所へ持っていき、上・中・下と選別される。
人参を隠したり勝手に売買したりする事が無いように、厳重な管理の基にすべてが行われたようです。
各村から持ち込まれる土人参の選別、格付け、水洗い、湯通し、陰干し、江戸への輸送と、将軍家御用という重責の下に、異郷に倒れた奉行の墓は、板荷の観音寺に三基並んであります。没月はいづれも繁忙期の8月、9月でした。
徳川幕府の人参への関与は、明治2年で終わりを告げます。
幕府崩壊して買い手を失った人参栽培者は、それでも作り続けるしかありませんでした。やがて、明治資本主義の萌芽と共に、再び人参に陽が当たる様になります。日光人参として今の中国へ輸出されました。
代表する人物は、安田善次郎でありましたが、地元からも人参から得た資金を、後年、麻産業の近代化を興し、当時財界で重きをなした鈴木要三も人参世話人の家系でした。
その十二 終わりの初めは大変だ
嘉永六年1853年7月米使ペリーは軍艦4隻で浦賀に来航、翌年はさらに9隻に増やして強く開国をせまり、風雲急を告げるご時世となった。
柿沼家は今宮神社、神職の家であります八代目、廣身30歳の時黒船が来航し、ハリスが来日して通商条約が始まったのが1856年、開国か攘夷か国論は大きく割れた。
柿沼廣身35歳の時、江戸に出て平田鉄胤の門に入って国学を修め、千葉周作の門人、宮和田光胤から北辰一刀流の目録を得て鹿沼に戻るや今宮神社の境内に塾を作り、子弟に教えた。
また幕府体制からの脱却を求める声が高まるなか勤皇思想も萌芽してきます。新体制を作ろうと言う人々を後になって勤皇の志士と言いました。
廣身も熱い血汐のたぎる同士、宇都宮藩の県勇記、水戸の藤田小四郎などと交わり奔走した。
やがて幕府に追われ多田忠三郎と変名して京から四国に渡った。明治まで後7年、やがて機は熟して鳥羽伏見の戦いが始まるや有栖川大総督の旗下に東征軍として江戸に進みました。
志なった廣身は鹿沼に帰ります。世は明治と改まり同7年に栃木県神道教導取締に就任、また日光二荒山神社の宮司となりました。この頃、中禅寺湖に魚はいませんでしたが廣身は模索の末、鯉を放し成功します、今の養殖の先がけに成ったのです。
今宮神社の鳥居の奉額は有栖川親王殿下の筆になるものです。廣身は明治26年・67歳で没します。その時殿下より下賜された榊の木があり、その前に有栖川親王殿下御下賜之榊と石柱に刻んであります。幕府から明治の動乱期を生きた有栖川宮と柿沼廣身の関係は浅からぬものであったのでしょう。
有栖川宮は皇女和宮と結婚することになっていましたが、和宮は朝廷と幕府の融和のため十四代、徳川家茂に嫁ぎました。
時代が大きく変わるとき、昔も今も人は懸命に生きる。
柿沼家は今宮神社、神職の家であります八代目、廣身30歳の時黒船が来航し、ハリスが来日して通商条約が始まったのが1856年、開国か攘夷か国論は大きく割れた。
柿沼廣身35歳の時、江戸に出て平田鉄胤の門に入って国学を修め、千葉周作の門人、宮和田光胤から北辰一刀流の目録を得て鹿沼に戻るや今宮神社の境内に塾を作り、子弟に教えた。
また幕府体制からの脱却を求める声が高まるなか勤皇思想も萌芽してきます。新体制を作ろうと言う人々を後になって勤皇の志士と言いました。
廣身も熱い血汐のたぎる同士、宇都宮藩の県勇記、水戸の藤田小四郎などと交わり奔走した。
やがて幕府に追われ多田忠三郎と変名して京から四国に渡った。明治まで後7年、やがて機は熟して鳥羽伏見の戦いが始まるや有栖川大総督の旗下に東征軍として江戸に進みました。
志なった廣身は鹿沼に帰ります。世は明治と改まり同7年に栃木県神道教導取締に就任、また日光二荒山神社の宮司となりました。この頃、中禅寺湖に魚はいませんでしたが廣身は模索の末、鯉を放し成功します、今の養殖の先がけに成ったのです。
今宮神社の鳥居の奉額は有栖川親王殿下の筆になるものです。廣身は明治26年・67歳で没します。その時殿下より下賜された榊の木があり、その前に有栖川親王殿下御下賜之榊と石柱に刻んであります。幕府から明治の動乱期を生きた有栖川宮と柿沼廣身の関係は浅からぬものであったのでしょう。
有栖川宮は皇女和宮と結婚することになっていましたが、和宮は朝廷と幕府の融和のため十四代、徳川家茂に嫁ぎました。
時代が大きく変わるとき、昔も今も人は懸命に生きる。